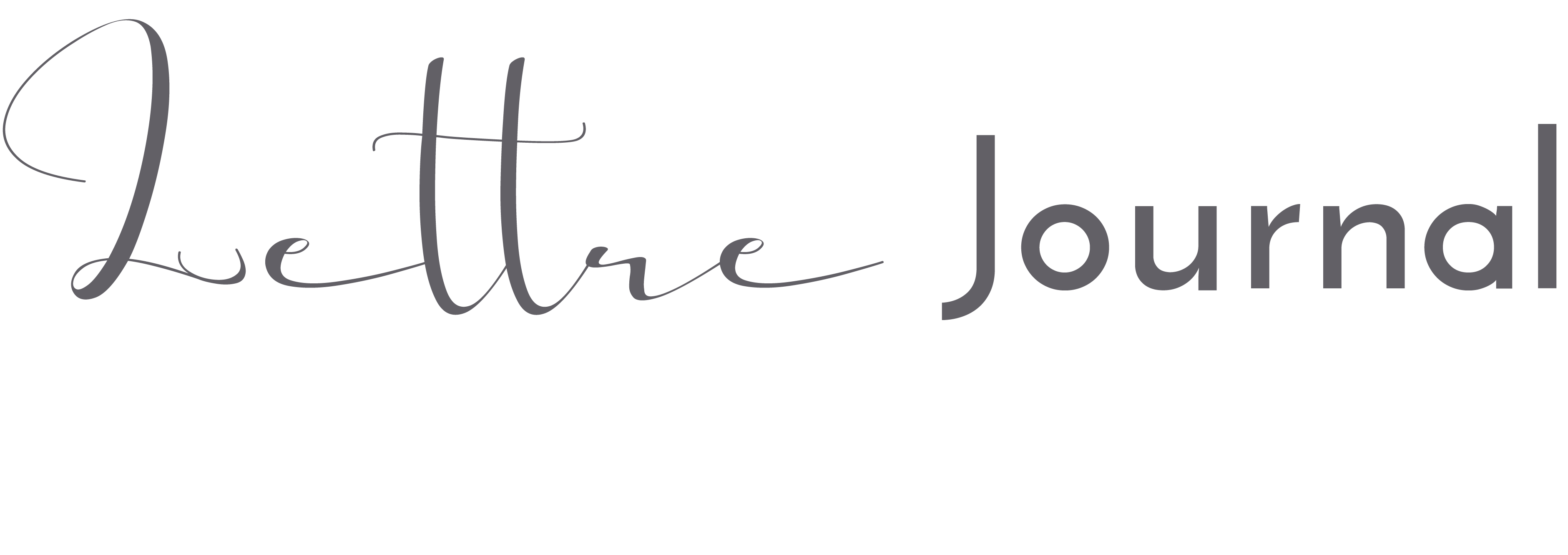紅茶には、ダージリンやアッサム、ウバなど品種がありますが、そのほかに「OP」や「BOP」などの表示があるものがあります。
また、紅茶好きなら「オレンジペコー」という言葉を聞いたことがあるでしょう。
これらは紅茶のサイズや形をあらわす等級(グレード)を示すものです。
等級(グレード)というと品質の良し悪しを比較したもののように感じますが、茶葉のサイズを揃えるために形状や大きさ、部位によって分類したもの。
美味しい紅茶を淹れるためには、茶葉の大きさや形状を揃えておくことが重要なのです。
基本的な紅茶の等級

| OP オレンジペコー | 枝先から2番目の小さな葉を含み、針金状の細長い葉。茶葉の長さが約7~11mm。 |
| P ペコー | 葉は大きめでよく揉まれてたもの。OPより短く針金状ではない。 |
| BOP ブロークンオレンジペコー | OPを揉捻する際にカットしたもので2~4mm。芯芽を多く含む。 |
| BP ブロークンペコー | BOPよりサイズが大きく、芯芽は含まれない。 |
| BOPF ブロークンオレンジペコーファニングス | BOPをふるいにかけたときに落ちる1~2mmの茶葉。香り、水色がよく上級品。 |
| D ダスト | 最も細かく1mm以下の粉状の茶葉。良質なものは香りが強く高値。 |
| SOUSHONG スーチョン | 茶木の下のほうにある比較的大きな茶葉。あまり紅茶には使われない。 |
| CTC製法 Crush,Tear,Curl | 茶葉をつぶし裂いて丸めた製法。ティーバッグに使われる。 |
ここに挙げた等級はほんの一部であり、茶園や地域によって等級のつけ方は異なり、それぞれの産地で紅茶の価値を高めようと等級を細かく分類する傾向にあります。
最も有名な紅茶の等級は、オレンジペコー

紅茶の等級の中で最も有名なのは、オレンジペコーでしょう。
オレンジという名前のせいか紅茶の種類やテイストと勘違いされることがありますが、オレンジペコーとは「OP」と表示される紅茶の等級です。
オレンジの味や香りがするわけではなく、茶木の枝先から2番目の芯芽を含む大き目の茶葉のことをオレンジペコーと分類しているのです。
オレンジペコーが有名な理由
どうしてオレンジペコーがここまで有名なのでしょうか。
それは、オレンジペコーがブレンドティーに多く使用されることが理由のようです。
なかでも有名なものではイギリスの老舗トワイニング社のブレンドディーで、昔は良質なセイロン茶のことをオレンジペコーと呼んでいたという記述もあり、オレンジペコーという名前が広まったと考えられています。
オレンジペコーの語源は?
「オレンジ」の前にまず「ペコー」の語源をご紹介します。
紅茶発祥の地、中国福建省では白く産毛が生えていることをあらわす「白毫(びゃくごう)」という言葉があり、福建省の言葉では「ペイカウ」というように発音されます。
茶葉はまだ芽が開かないうちは葉に産毛が生えていることから、茶葉を「白毫」と呼ぶようになり、これが英語に置き換わって「pekoeo(ペコー)」となったそう。
では、オレンジは?というと、
- 白毫が光にあたりオレンジ色に見えた
- 紅茶の水色がオレンジ色だから
ともいわれていますが、由来ははっきりしていません。
ですが、このことからもオレンジペコーが果実のオレンジとは関係がないことがわかっていただけると思います。