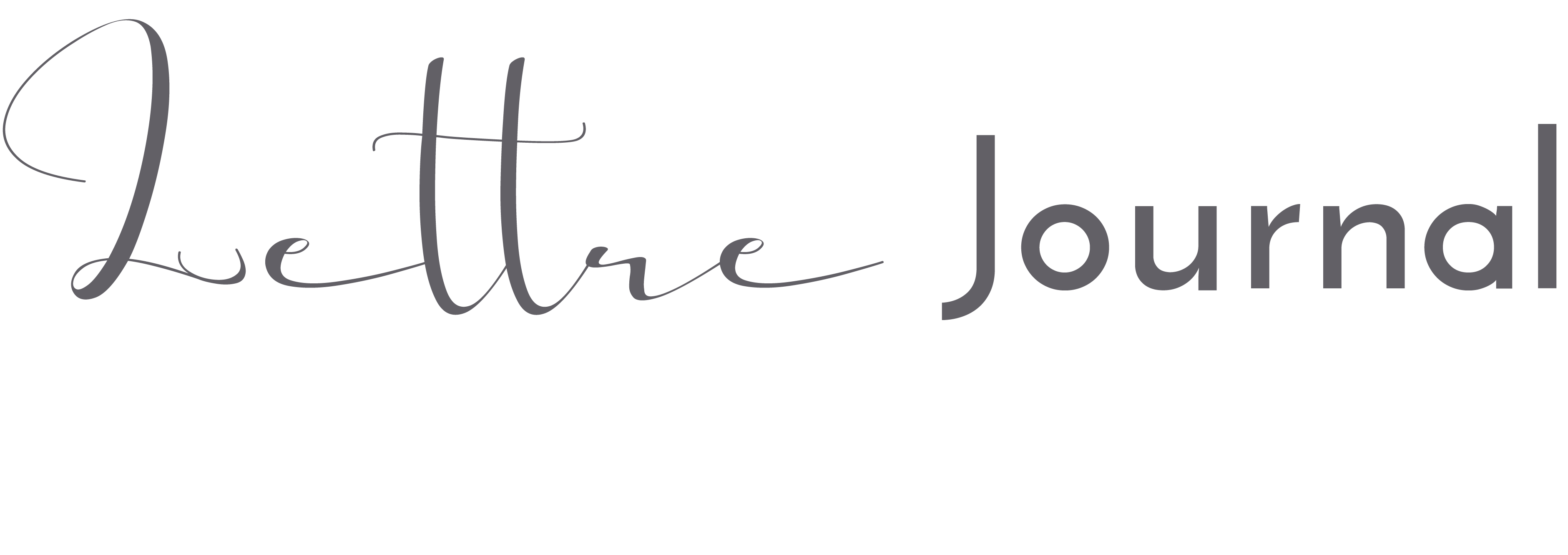11月1日は「紅茶の日」です。
この日は紅茶関連のイベントが多く開かれており年々広まっていますが、まだご存知ない方も多いのではないでしょうか?
今回は「紅茶の日」が制定された歴史的背景を紐解いていきましょう。
なぜ、11月1日は紅茶の日?

11月1日が「紅茶の日」に制定されたのは、1983年でした。
制定したのは日本紅茶協会で、紅茶輸入業、紅茶関連商品取扱業者、紅茶生産国の茶業振興局から構成されています。
少しずつ空気が冷たくなり温かい紅茶が恋しくなる季節ですが、11月1日が紅茶の日に決まった理由は江戸時代まで遡ります。
初めて外国の正式な茶会に招かれた日本人
1791年(寛政3年)11月、海難に遭いロシアに漂着し10年近くロシアに滞在していた日本人、大黒屋光太夫は女帝ロシアのエカテリーナ2世に茶会に招かれます。
そして、この日が日本人として初めて外国での正式な茶会で紅茶を嗜んだ公式記録となっています。
なお、大黒屋光太夫が飲んだのは砂糖とミルクを加えたミルクティーだったそうです。
この歴史的な背景にちなみ、1983年に11月1日が「紅茶の日」と制定され、これ以降紅茶の啓発や普及のために各地で紅茶に関するイベントやセミナーが開催されるようになりました。
大黒屋光太夫のその後
紅茶の話から少し逸れますが、大黒屋光太夫について触れてみましょう。
大黒屋光太夫は伊勢の国(現在の三重県)の船乗りでしたが、1783年船員とともに紀州藩の囲い米を江戸に運ぶ途中、駿河湾付近で暴風雨に遭い航路を外れ漂流し、アムチトカ島(アラスカからカムチャッカ半島にかけてのびる列島のひとつ)に流れ着きました。
漂流した距離は直線で約3,700kmほどもあり、命を落とさず生きて流れ着いたことは本当に奇跡です。
大黒屋光太夫はアムチトカ島で先住民やアザラシの毛皮などを求めるロシア商人に遭遇し、ロシア語を習得して一緒に島を脱出することになりましたが、またもや災難に見舞われ迎えに来たロシア船が接岸に失敗し大破してしまうのです。
そこで、船の構造に詳しい大黒屋光太夫らがロシア人を指揮し、大破した船から材料を得て脱出用の船を建造、ロシアのカムチャッカに到着することができました。
大黒屋光太夫は帰国を願い出ますが、日本との国交を望んでいるロシアの総督府から帰国を拒絶されなかなか認めらず月日が経っていきました。
ロシアに到着してから4年後に熱意が通じ女帝エカテリーナ2世と謁見、茶会に招かれた翌年1792年、漂流から約9年後に根室港入りして帰国することができたのです。
エカテリーナ2世は大黒屋光太夫の境遇を嘆き、直接煙草入れを賜ったと伝えられています。
大黒屋光太夫は鎖国中の日本において数少ない異国見聞者となり、将軍家斉の前で聞き取りを受け蘭学者の浦川甫周が大黒屋光太夫の口述をもとに「北槎聞略」という書物を編集し蘭学に寄与しました。
このように、波乱万丈な大黒屋光太夫の生涯は、いくつかの小説となっています。
その中で、作家の井上靖は大黒屋光太夫の生涯を描いた「おろしや国酔夢譚」では、帰国後は危険人物として扱われ不自由な生活を送ったかのように描かれています。
しかし、実際には蘭学者である大槻玄沢が催したオランダ正月を祝う会にも招待されており、多くの知識人たちと交友をもち、江戸の薬園に居宅をもらって比較的自由に暮らしていたようです。
「紅茶の日」におすすめの紅茶

大黒屋光太夫がエカテリーナ2世に謁見したのは、ロシア帝国の帝都サンクトペテルブルグでした。
「KUSUMI TEA」には、この都市の名前「サンクトペテルブルグ」という名前の紅茶があります。
ベルガモットの香りを纏わせたアールグレイをベースに、キャラメル、レッドフルーツ、バニラをブレンドした芳しい風味が特徴の紅茶です。
まとめ
大黒屋光太夫が日本人として初めて外国の正式な茶会に招かれてから233年、現在の日本では海外の紅茶のみならず国産の紅茶「和紅茶」の人気が高まってきています。
そして、紅茶の日である11月1日頃は、少し空気が冷たく秋の終わりを感じさせ、温かい紅茶がより美味しく感じられるでしょう。
ぜひお好きな紅茶を淹れて、ゆっくりティータイムをお過ごしください。